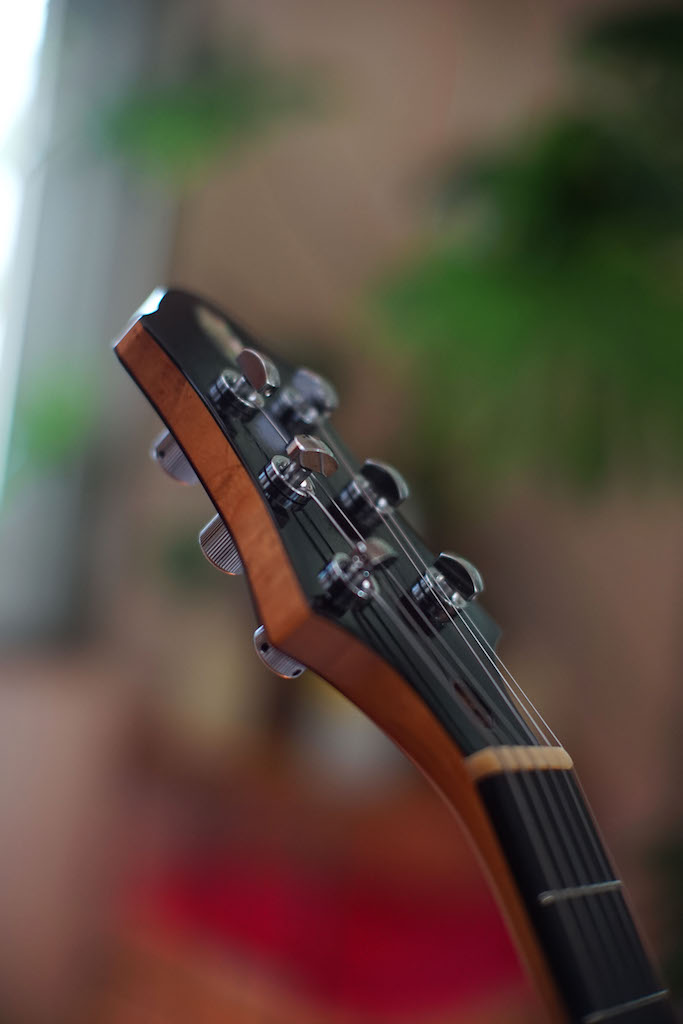Black Walnut.
4年ほど寝かせてあったブラックウォルナットを出して来ました。
一抱えもあるんで,素手では運びたくないヤツです(笑。
うっすらと杢も見えるのですが,こういうのこそ厄介です。
樹木の成長に無理がかかっている場所だったり節のそばだったりすることが多いんです。ってことは,,,「切るのがシンドい」。
広いところで幅が500mmを超えていますので,最初から「手鋸」は除外。
厚さに余裕がありそうだったので,久しぶりにチェーンソーの登場です。
いやいや,これは「切る」んじゃなくて「掘る」のに近いですね。
準備から2時間ほどで切断完了。
チェーンソーは途中で5回研ぎました。
っていうかそのくらい休憩が必要だったって訳です(笑。
割れの小さい方を選んで始めます。割れの部分を逃げて逃げて15inch Bodyのサイズに切り出して行きます。
うっすら杢はこの厚さに落としてもまだ残っていますね。
シメシメ,,。
ところが厚み方向への「割れ」は残っています。
なんとかアーチの削り出しの範疇に見えますが,これは削って見なければわからないですね。
これがアーチトップを作る時の最初の難題です。
入り皮とか節とか,削っていって出て来ることもあるから厄介ですよね,,,。
久しぶりに小春日和の札幌です。