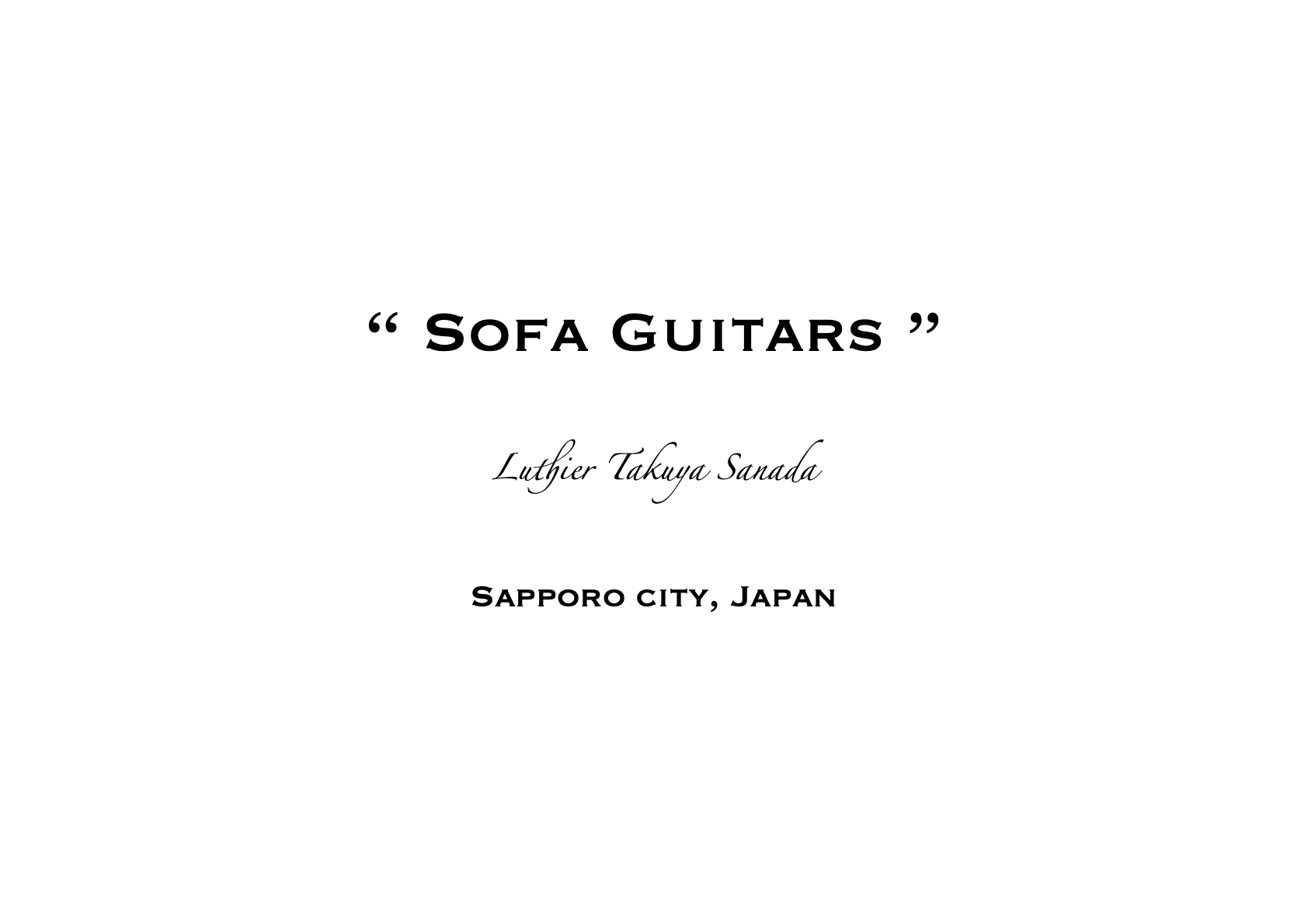午後,2本目のトップも削り出します。
アーチの形状は,テンプレートなども作りにくいですよね。
寸分違わぬ,,とは行かないかもしれませんが,「体が覚えている」事を信じて削ります。
(こうだよな,うんうん,,ブツブツ,,)

こっちのFlameは,どんな感じでしょ。
なんか1本目と似てるな,,同じフリックだったでしょうか,,。

はて,確か識別名称ありましたよね,,
フランツとミレナ,,
あるいはNo.3とNo.4,,
あるいは035と036,,,
うーん,覚えられる気がしません(笑。
どっちがどっちやら,書いておかないと,,。

チビカンナで,ベース側半分をザザッと削ったところ。
うん,これも綺麗なCurlyですね。
なぜか耐熱手袋をはめてミニカンナ。
滑らなくていい感じ。

ざっと削り終えたところで,霧吹きで「水引き」をして記念撮影。

あれ,どっちがフランツでしたっけ,,,(笑。
文化の日なので,たくさん写真を載せました(笑。
11.75inch Archtop 14inch 14inch archtop 14inch Prototype 15inch Archtop 17inch Archtop Alembic Amek archtop Bass Bubinga Chaki Curlymaple Double Cutaway Ebony EF28-70 2.8L Elmarit-M28mmF2.8 Elmarit-R 24mmF2.8 Elmarit-R180mmF2.8 Explorer修理 Gibson Ibanez in case of Inlay Jingle JohnnySmith Keyaki Kluson Noctilux 50mmF1.0 M Nylon repair Rupes Semi-Acoustic Shellac Summarex85mmF1.5L Summaron35mmF2.8M Summicron-R 50mmF2 SuperAngulon21mm F3.4 M Tailpiece ToneWoods Tools Walnut アーチトップギター製作 ギター製作 左市弘