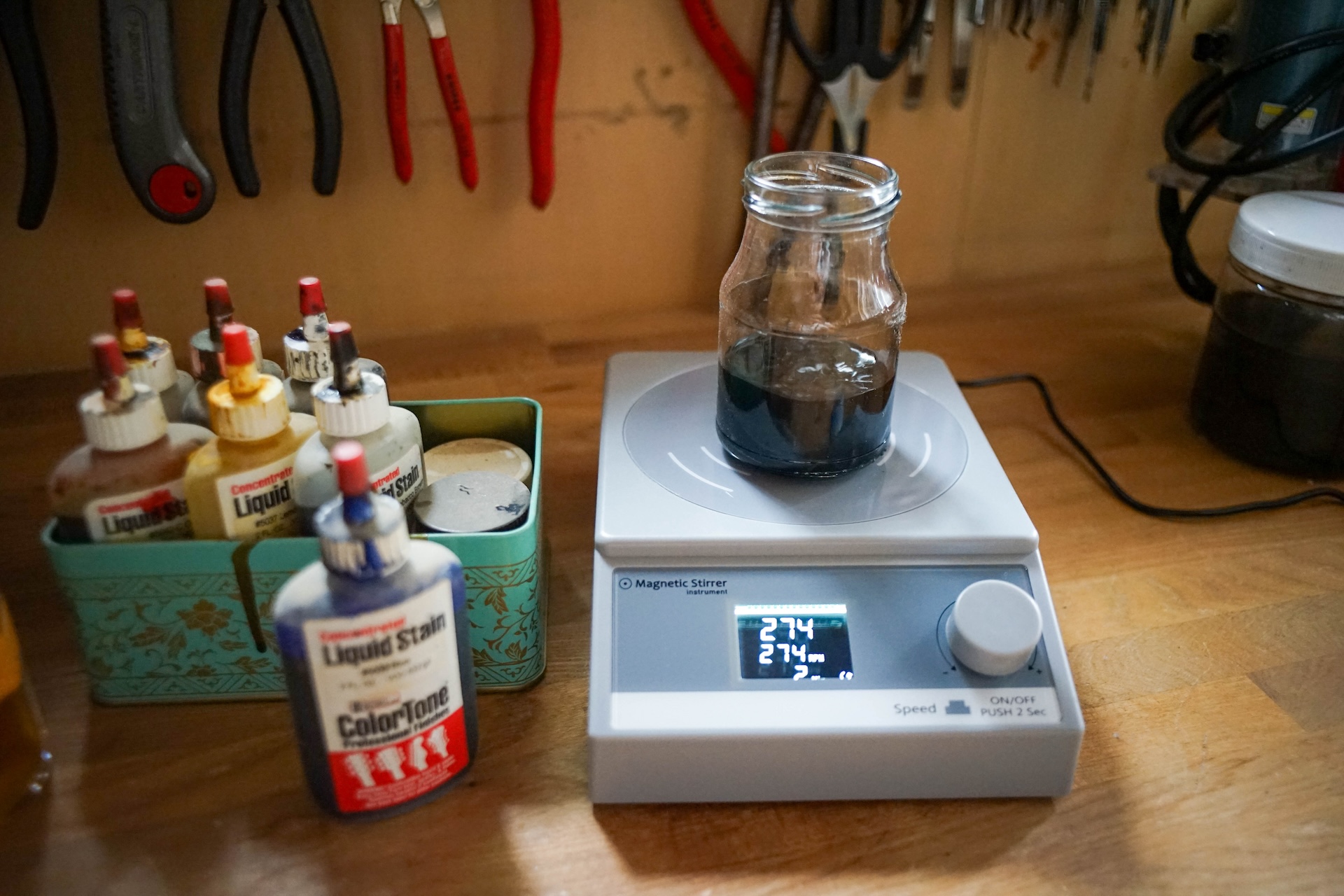魂ってどこにあるんですかね?(笑。
心とか魂って,体のどこにある?問題。
脳の中に決まってんじゃん!とか,DNAとか,血液??あれ?,,ってな具合で。
どっかに「個性」とか司ってる部分ってあるんですかね,,
って,そんな難しいこと,私なんぞには分かりませんが。
ただ,今回このジョニーさんの大手術して,弦を張って最初に出てきた音,手術前と比べてどうだったと思いますか?。
「ざっくり元と同じ音」でした。
もちろん,音量はちょっと大きくなったり,,とか,前より音程が聞き取りやすいかも,,とか,ピックアップと弦との距離が正しくなったので,アンプからの出音が「ちゃんとした」とかはありますが,全く同じ年代の全く同じ工場で作られた同じモデルと比べても明らかに違う,この楽器の「声」でした。
ジョニーさんにしてみれば,「やべー,もうちょっとで死ぬとこだったぜ,,」ってくらいの大手術ですよね。
ボディから首(ネック)を一度取って,角度を変えて,フィンガーボードは作り替えて,,。
私的には,ネックジョイントって,その楽器の音のコアだと感じることが多いのですが,ネックジョイントをやりかえても,ニュアンスは変わらなかったです。
ある意味,それで「正しい」のだと思いますが。
ストラディバリの時代のヴァイオリンは,そのほとんどが今の基準より短いショートスケールのネックだったので,現存している楽器のほとんどは,ネック部分だけ「ロングスケール」になるように別の人が入れ替えているって聞いたことがあります。
ボディとヘッド(スクロール)だけは,製作者のものなのだとか,,。
じゃ,ネックって楽器の個性には関係ないんじゃね?,,
となるかもしれませんが,ご承知の通り,ネックの材質で響き方,違いますよね,,,。
じゃ,楽器の個性ってどこに???(笑。
ストラディバリのレントゲン写真ってありますよね,,でも,わかんないみたいですよね,,彼の秘密。
まぁ,今回はフィンガーボード以外は「元のまま」ですので,「当然」なのかもしれませんが,,,。
などと,リペアを終えて実際に音を出してみた「ファーストインプレッション」でした。
つまんない話ですんません,,(笑。