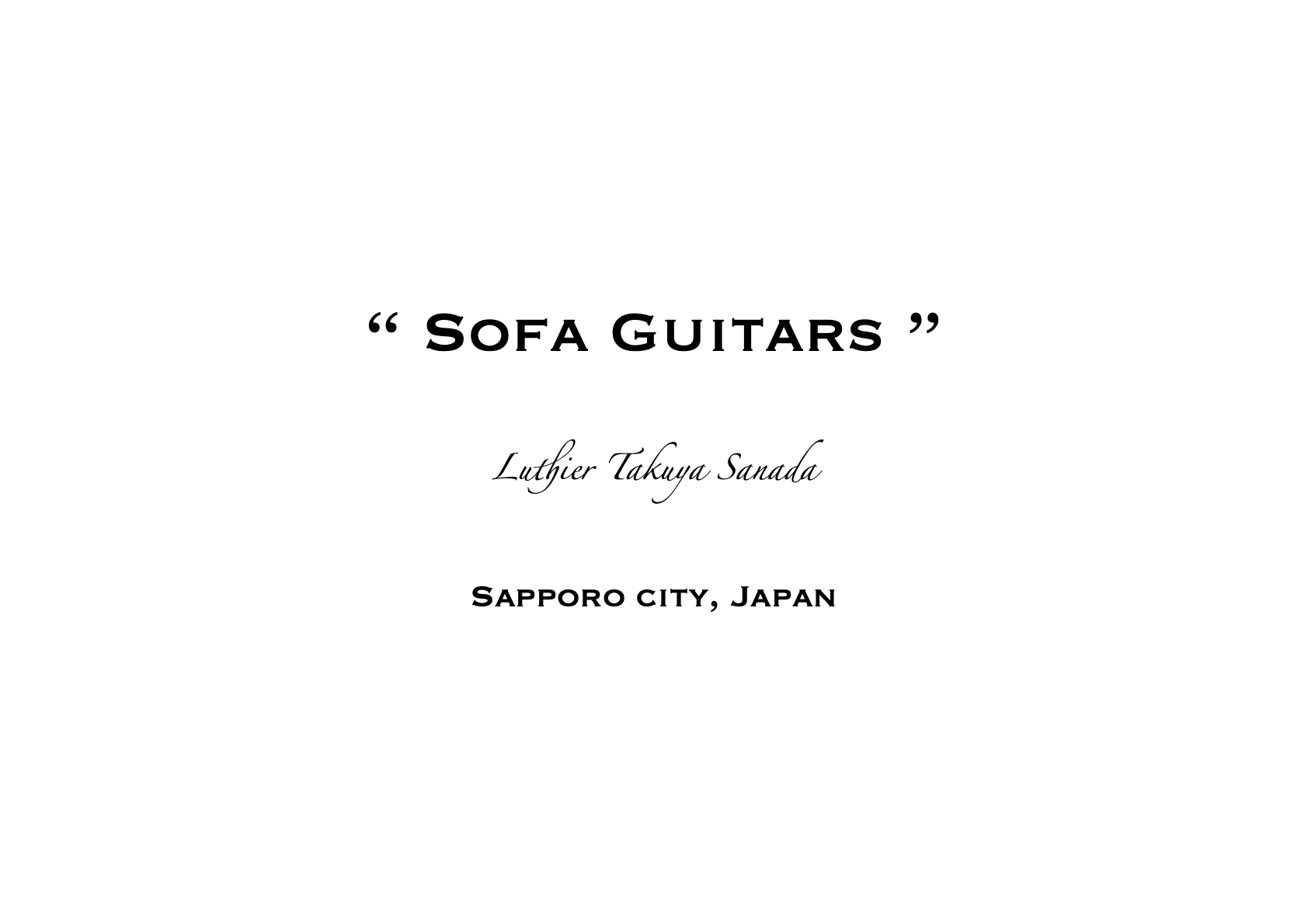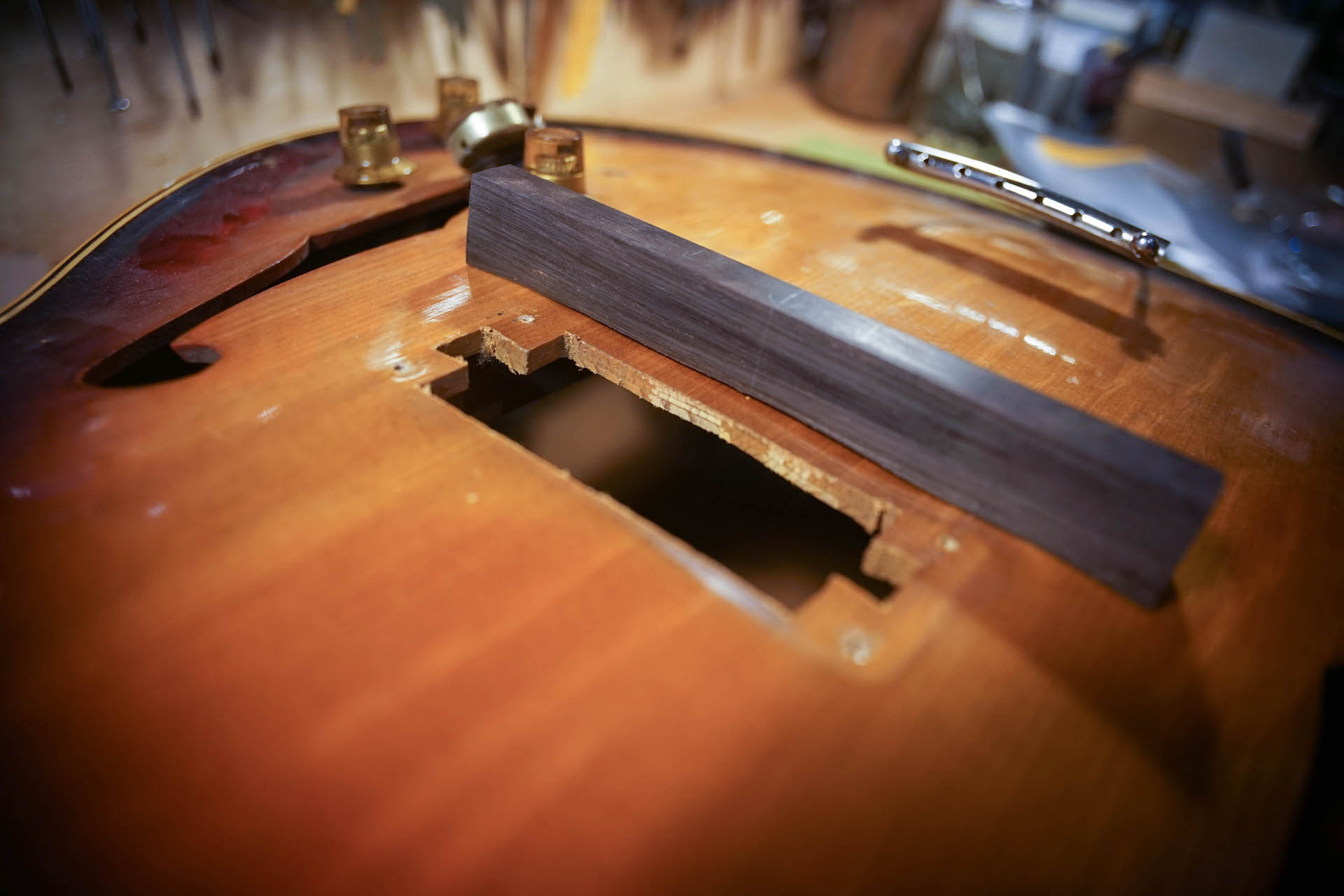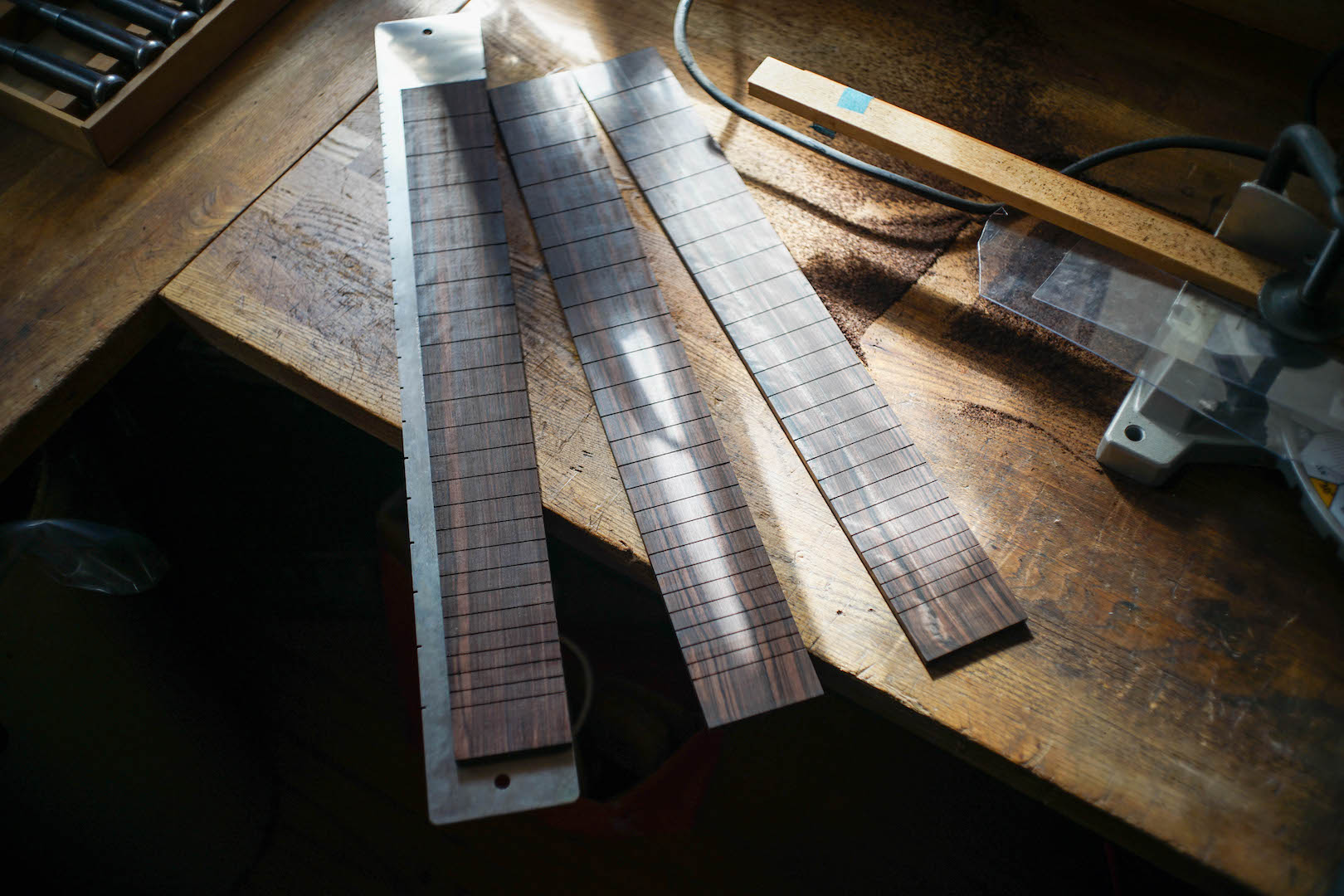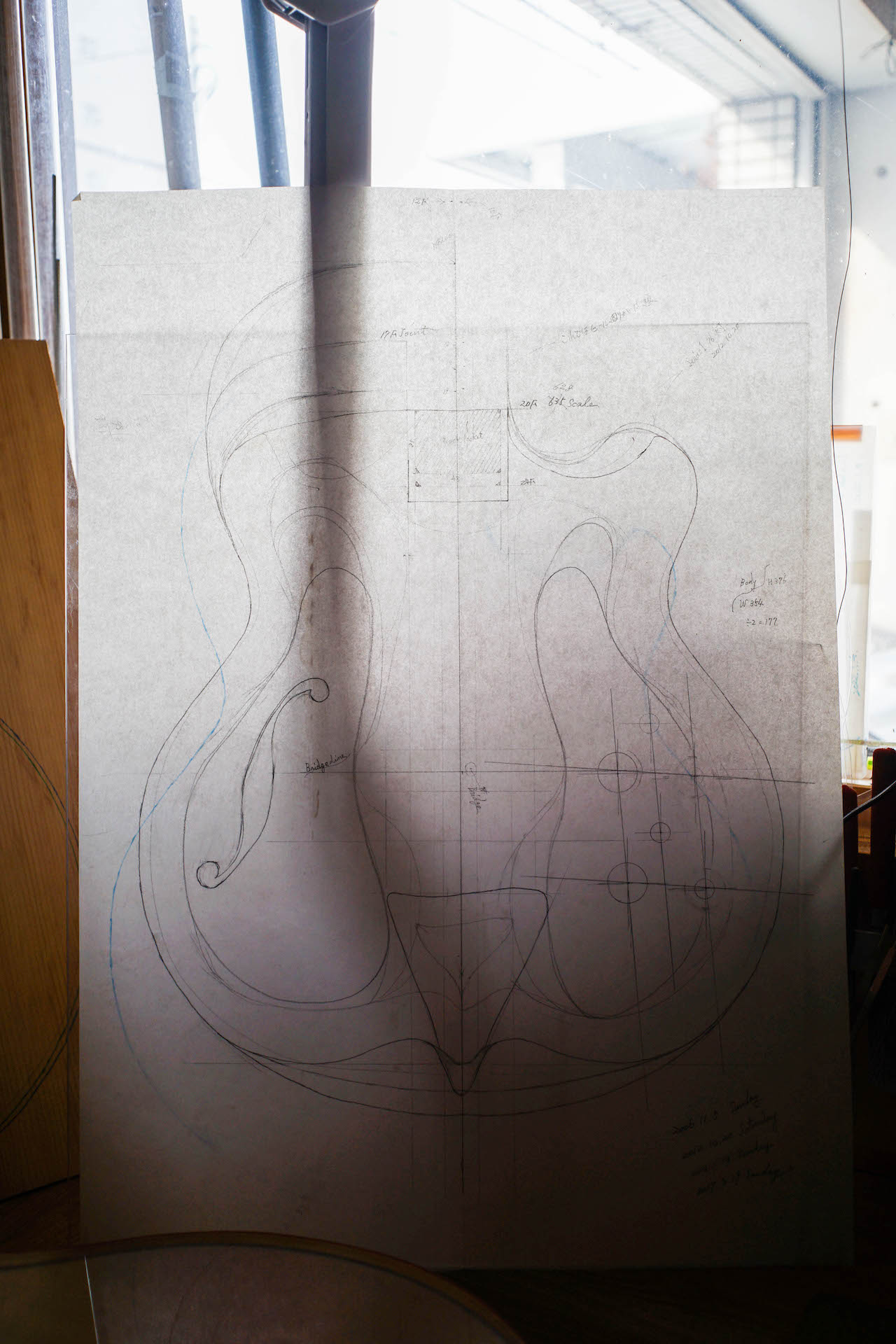
新しい試みの考察。
っていうか,
このデッサン,2006年から書いては消し,描いては消してきたものです。
なので,線がたくさんありすぎて,自分でもどれがどれだかわからなくなってます(笑。
でも,この線の中から,自分が見たいアウトラインを見つけていくための大事なメモです。
んで,今回新しいアウトラインを描いたのか,,というと,,,

全然そうじゃなかったです(笑。
以前作った15インチのSemi-Hollowのカッタウェイの部分の曲線を描き変えただけでした(笑。
自分にとっての完全に新しいアウトラインを採用するのは,「次」にします。
作りかけて途中半端になってるのを,まず仕上げて行く事にします。
「作りかけ」が段々小山になってましたので(笑。という事で,
やりかけの「Semi-Hollow」の製作,再開です。

中空部分を作るボディの真ん中は,桂です。
軽くて密な素材。
海外では,大抵この部分はマホガニーでやる人が多いですよね。
この形までは既に終えています。
平面出しするのに,カンナを出してきたのですが,最近全く調整もしてなかったので,赤樫台の乱菊,調子が出ませんでした。
っていうか,こんな風に切り出してしまったら,「寸八」のカンナはちょっと大きすぎますね。
洋ガンナを出してきて収めました。
久しぶりにカンナ,ちゃんと調整しましょう。

バック用のCurly Mapleは既にアウトラインを切り出してあったのですが,
トップ材が決まってませんでした。
で,引っ張り出してきたのは,
これも既にセンタージョイントが済んでいるスプルースです。
ベアクロウのちょっと面白い木目。
こいつに決めました。
スプルーストップは,見た目,超地味かもしれませんが,アコギ寄りのイメージで行こうかな,,と。
作りかけの材料ばかりなので,ジャンジャン進めます。