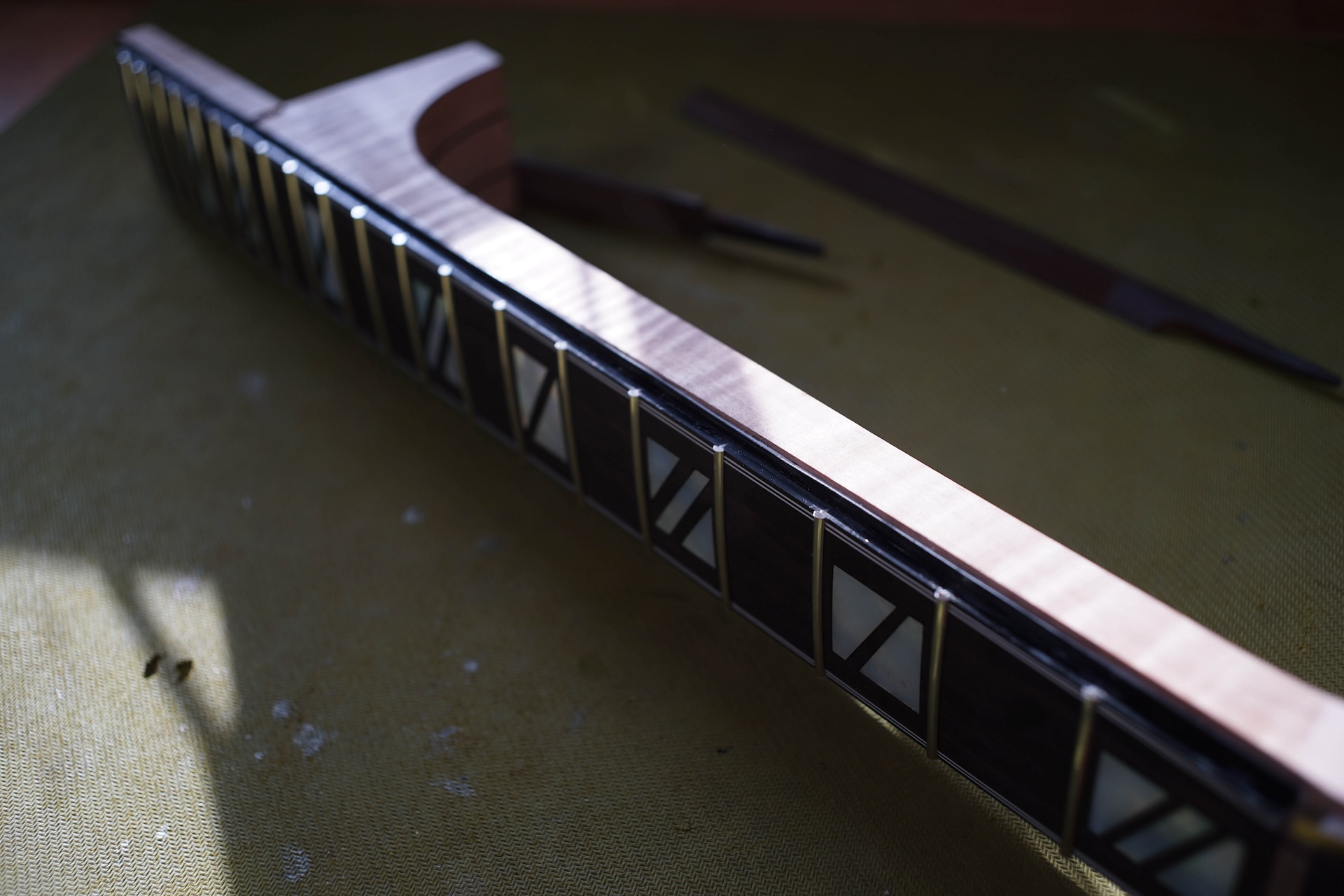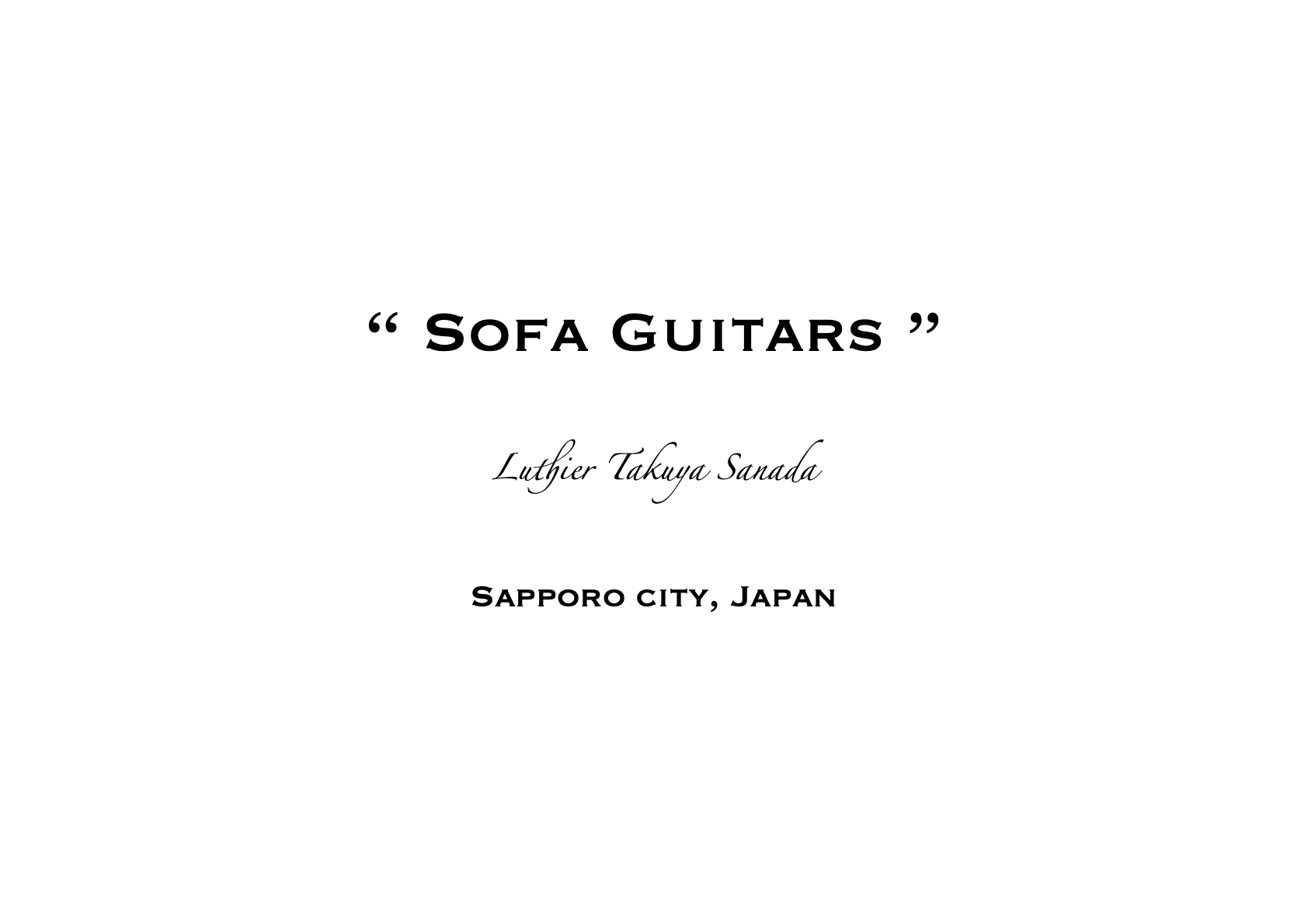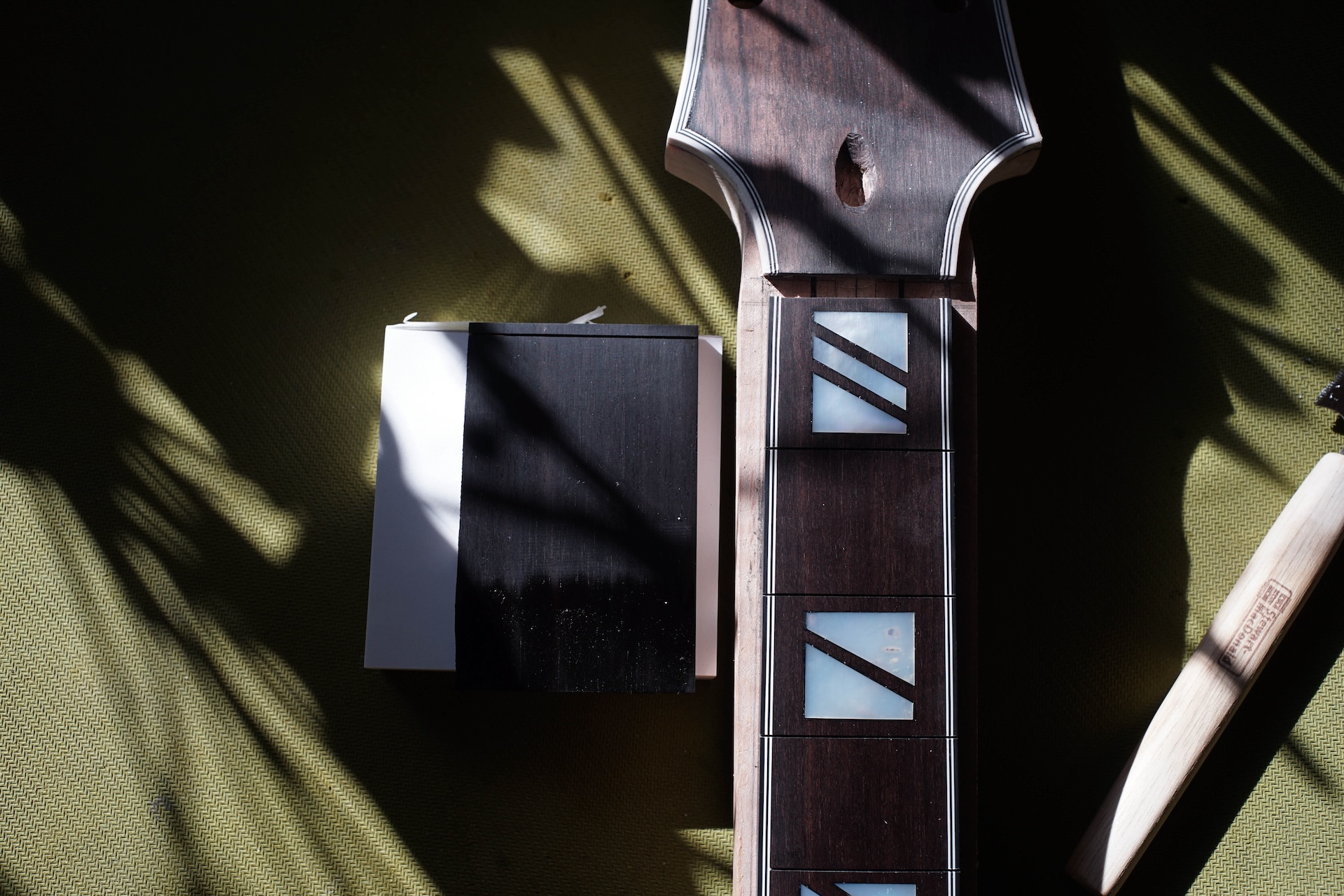黒く染めるには。
真っ黒なEbonyがなかなか手に入らないのは,私らみたいな個人製作家だけではなく,大手メーカーも同じなようです。
っていうか,古い数枚の指板材だったら,「金に糸目をつけなければ」今でも多少は手に入りますよね。
だから「一山」単位で入手しなければならない大手ほど,そうなのかもしれません。
っていうことで(笑,StewMac(米国のギター製作用品の販売店)が勧めているのがこれ。
Higginsというメーカーの黒いインクです。
乾く前なら水に溶けますので,筆をダメにせずに済むのは良いです。
これ,本来はなんのためのインクなんでしょ,,。
よくわかりませんが,木材に塗って,翌日「ボロ切れ」で拭いて,
また一晩おいて,スチールウールで磨いて終わり,,,
という手順まで紹介されています。
ヘッドに貼った縞黒檀の色具合がちょっと薄くて残念だったので,染めてみます。
これまでもテールピースを染めたことはありましたが,ヘッドは初めてかな。
黒檀のフィンガーボードも貼りました。
Johnnyさんは,,,
バインディングの白・黒・白・黒まで完了。
アールを取ってフレットを打つ準備。
傷だらけの Body ,どの程度修復しましょうか,,。
流行の「Heavyレリック」って言えば,このままでいいのかも,,(笑。